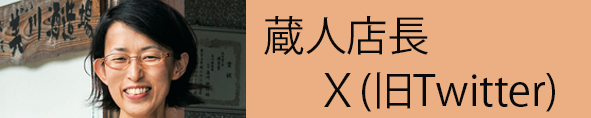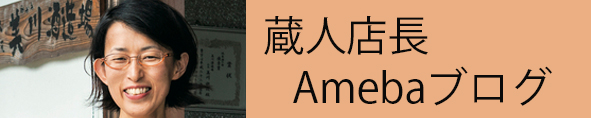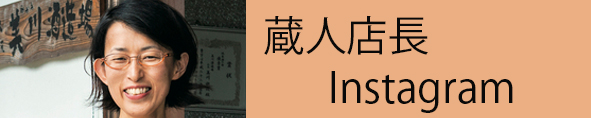| 越前 木槽(きぶね)搾り | |
木槽(ぶね)搾りとは。。。。。
| |
| 舞美人の木槽搾り 手順 | |
| 1、もろみを酒袋にいれます。 | |
 | 仕込みタンクから、ポンプで運ばれてきたもろみ(酒母に水、麹、蒸米を仕込んだもので、清酒の母体となるもの)を酒袋の中に入れる作業です。
|
| |
| 2、酒袋を木槽に並べます。 | |
 | 酒袋を、一つ一つ丁寧に並べていきます。口は、何かで止めてあるのではなく、下に折り曲げてあるだけですが、不思議と中身は出てきません。 袋取りと呼ばれる作業です。 蔵元杜氏の技が発揮されます。 |
| |
| 3.どんどん酒袋を積み上げます | |
 | きれいに、どんどんどんどん積み上げていきます。 |
| |
| 4.一袋ずつ丁寧に | |
 | 1~3までの作業をを、繰り返し繰り返し続けます。
ここまでくると、重みで槽口(ふなくち)からちょろちょろと新酒が出始めます。蔵に新酒の香りが立ち込め、造り手として嬉しい瞬間です。 |
 | |
| |
| 5.ふたをかぶせます。 | |
 |
木槽(きぶね)の蓋を積み上げた酒袋の上にせます。 |
| |
 | 木槽(きぶね)の槽口(ふなくち)です。 出ていたばかりの新酒を、ここからすくって飲むと、最高の美味しさです。 |
| |
| 6.圧力をかける | |
 |
蓋の上に、非常に重い木片をいくつも積み上げ、その上から油圧による圧力をかけます。 その時、「ゴンゴンゴン」という多きな音がするのですが、舞美人の酒蔵の名物になっています。搾っている間は、常に異常がないか緊張しています。
酒袋のもろみの量や、積み具合などが悪いと、中で破裂しもろみが蔵の天井まで、飛び散ってしまいす。
|
木槽(きぶね)搾りをするためには、どの作業一つとっても手を抜けるところはありません。ですが、大吟醸や鑑評会用のお酒など高級酒の搾りにはこの木槽(きぶね)使用しているという酒蔵さんもあるぐらい、その実力は認められています。
| |
メンテナンスには柿渋を使用しています。
毎年塗り重ねることで、見た目もあめ色に美しく輝きます。
 |  |